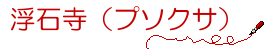|
2008年4月 |
| 栄州市(ヨンジュシ)の、北側には小白山(ソペクサン:1.439m)系が連なっている、この山系の鳳凰山南麓に位置する「浮石寺(プソクサ)」を訪ねた。 この寺は新羅文武王(676年)時代に義相大師によって創建されました。鳳停寺の極楽殿とともに、韓国におけるもっとも古い木造建築物があると紹介されている。解体修理の際に発見された「墨書銘」によれば現在の建物は1376年に建てられたものであると言われている。 「浮石寺」に向かうが昼過ぎになったので道端にあった食堂のテンジャンチゲ(韓国味噌汁とご飯)を食べたが味はイマイチであった。このような田舎では仕方がないかもしれないと納得して浮石寺に着いてびっくり、広い駐車場とお土産物屋がたくさん並んでいるではないか、食べたいなと思った「安東塩サバ料理」も看板に出ている。ここで昼食にすれば良かったが初めての訪問だから仕方がない。この風景からかなりの参拝者が訪れるのだろう、韓国人のこの寺にかける深い思いが伝わってきた。 |
|||||
|
|||||
 少し登ったところにある山門の両側はりんご園と高麗ニンジン畑 |
|||||
 |
|||||
| 両脇の緑が門の色彩を引き立てている | |||||
|
|||||
| 駐車場から少し歩くと券買所があり文化財観覧料として一人1200ウオン支払う、ここでは日本語の案内書はない、また境内の説明文も英語、中国語だけであった。『太白山浮石寺』と書かれた山門をくぐる、更にしばらく登りの参道を歩くと四天王が両脇を固める天王門にたどり着きます。 ここから直ぐ境内かと思ったがまだ登りの坂を歩き20段ぐらいの階段がいくつか登る。後で話を聞けば国宝の無量寿殿までは108段の石段を登ることになるようだ。 鳳凰山浮石寺の額が見える梵鐘楼の下をくぐるとその奥に安養楼(安養は極楽を意味する)が見える。石段を登ると上に浮石寺、下に安養門と書かれてる扁額の下の石段を数段登ると。奥に国宝の無量寿殿が一段と高いところにあります。建物には丹青の鮮やかな色使いがほとんど使われておらず、日本のお寺のように古色を感じられる木造建築が建ち並んでいます。 |
|||||
 背景の山と安養楼と奥の本殿の無量寿殿の風景が美しい |
|||||
 国宝の無量寿殿 |
|||||
|
|||||
 無量寿殿の広場から振り返ると雄大な山の風景が見渡せます。ふと空を見ると急に天候が悪化してきたようだ、 背後の山から真っ黒の雲が張り出し雷も鳴り始めました。 |
|||||
| 無量寿殿の左手奥に浮石寺という名前の由来の浮石がある。長さが5〜6大きな平たい石が崖に沿って有ります、この石には「浮石」と刻まれています。「浮石」の伝説は以前読んだ桑野 淳一著「韓国古寺紀行」には次のように紹介されている。 | |||||
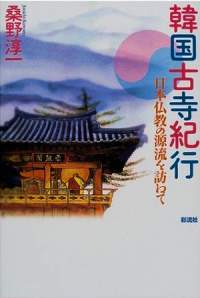 義湘は660年に山東半島に上陸し、托鉢しながら長安へ入ることに成功する。その途中で出会ったのが善妙という女性であった。善妙は義湘にこがれる恋慕の情を告白する。学問途上の義湘はこれを断って、長安は終南山に赴き、学門に精進する。善妙は義湘への恋慕の念断ち難く、十年間供養を続ける。 帰路、義湘がそこに立ち寄ると、善妙は待っていて、以降終世義湘を守ると誓いを立てる。義湘が船に乗ると、善妙は海に身を投げ、竜となって船を守る。 義湘が唐で学んだ華厳を説こうとして鳳凰山に至ると、不法者の一団がじゃまをする。すると竜の善妙は巨石となって覆いかぶさり、一団を威嚇して追い出す。その結果、義湘は無事に華厳を説くことが出来た。 その伝説の竜がこの天蓋の竜である。またその「浮石」と書かれた大石も無量寿殿の西側裏手に回ると見ることが出来る。寺名もここから由来したのはいうまでもない。 また岩の上には三層の石塔があり、後方には思い一途な善妙のために善妙閣がある。 |
|||||
|
|||||
| ここまで来たとき急に雨が降りだした、同行のT氏は疲れたので山門で待っているというので、私一人で無量寿殿の裏を150m近く登ると在るという「祖師堂」までせっかく来たので登ることにした。ここには伝説になっている「ソンビファ」という植物があるというので是非見たい一心で雨が激しなったが登って行くと、右の一段高い所に「祖師堂」の表示があった。 堂の前に出ると金網に囲まれた小さな植物があった。この植物がソンビファ(禅扉花)である、「義湘大師が土に刺した杖であり、以後水もやらずこのように生きているのだ」と運転手の金さんが話してくれたが・・・この伝説も伝説だから仕方がないが・・葉を煎じて飲めば子が授かるという話も聞いたのでいずれにしても信仰とはいろいろな話が付随して出てきて面白い。 この植物は一体何であろうか興味があるがこれ以上解らない、後で調査することとして雨が強くなったので写真だけ撮ってすぐに山門で待っているT氏のところに戻った。 |
|||||
|
|||||
戻る |
| TOPへ |