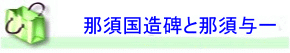 |
|
|
2008年3月
|
|
|
その昔、シベリア地方から南下した北方モンゴロイドの一部は中国の遼寧に住み着き、更に南下して朝鮮半島の高句麗、百済に住み、更に南下して海を渡り日本に住み着いたと各種の歴史書にある。特に栄華を誇った百済が660年に滅亡した時は多くの百済人が日本に渡った、当時の先進文化をもった彼らは日本で飛鳥文化の花を開かせてくれた。 |
那珂川沿いに国道294号線を黒羽に向かって行くと左側にこんもりとした老杉の森がある。ここに笠石神社(大田原市湯津上)が鎮座し、ご神体として「国宝・那須国造碑」が鞘堂(覆い堂)の中に安置されています。 |
 |
|
|
那須国造碑のある笠石神社
|
| 日本三古碑の一つといわれる那須国造碑の大きさは、碑の上部に乗せた笠石を除いた高さは1.2m、幅は最上部で42cm、最下部で49cm、厚さは約40cmで、石材は近くの八溝山地の花崗岩を用いている。碑の表面は平らに磨き、ここに1行19文字で8行、計152文字を整然と並べて陰刻され書体は中国の六朝風のものであるという。 碑文の最初の3行に歴史上重要な内容を記している。 「永昌元年4月飛鳥浄御原大宮(持統天皇)より、那須国造の追大壱(なすのついだいいち)那須直韋提(なすのあたえいで)は評督(=郡司)を賜ったが、庚子(かのえ)の年(文武天皇4年=700年)正月二日、辰の時刻(午前八時)に死去したので、意斯麻呂(那須直韋提の子?)らは父の遺徳をたたえ、碑を建てて偲び銘した。 おおよその意味は次の通り。 「父は広来津君(ひろきつのきみ)の後裔で那須国の棟梁であった、一生のうち、追大壱の位を与えられ、さらに那須評督に任命されて、二度の栄光に恵まれた。私たち子は、どんなに苦しいことがあっても、これまで受けたご恩に報いなければならない。孝養をつくす子は父の教えを守りつづけよう」
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
福原玄性寺にある供養碑は、那須与一公とその一族のために建てられたものと伝えられています。「伝えられている」とか「いわれている」という表現を使っているのは学実的な確証がないのである。しかしそれでも良いのではないか、那須与一という人物がこの地方から出て「扇の的」の伝説の元になっていることで十分である。
|
| 戻る |







